■仲間と共に強くなるための技法追求
坂出道院入門から3年目の昭和30年(1955)、森は総本部に転籍し四段を許された。
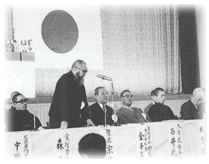 |
昭和37~38年頃、森大範士(左端。右隣、宗道臣開祖)が実行委員長を務めて開催された第一回兵庫県大会。 |
この頃になると、かつて「ケンカは先手必勝」と暴れた少年も、少林寺拳法によつて次第に考えが変わってきたという。森は言った。「技が始まる前に15~20分、開祖の話があるわけです。また、そこで誓句、誓願、道訓、信条を唱えるのです。礼儀を守り、平和を守るというのを毎回毎回100編も唱えていれば1回くらいは『そういう風にしなければ』という気になつてくる。
武道を究極まで突き詰めると、最終的には“相手を殺してしまわないと完全に勝ったことにならない”というところまで来るでしょう。その死の恐怖に打ち勝つために剣術家は禅をやったりするわけですが、少林寺拳法の技はすべて護身の技術だというのです。
護身の技術で、組手主体ですから、相手がいないと修行できない。相手もうまくならないと自分もうまくならないというところがあるのです。
だから、自分だけでなく仲間も強くしてやろうという気に自然となるのです。
演武にしてもそうです。演武というとただ見せるためのものと思う人もいるかもしれませんが、演武において連反攻できる、連続的に動けるということは、実際の戦いにも活きる訓練なのです」開祖・宗道臣の教えは実際的だった。世を正すためには、勝てなくてはいけない。しかし、一人の力など多寡がしれている。本当に強くなるためには、仲間を増やし、ともに強くなるのがいい。開祖の技に感銘を受けた森だったが、開祖はただ技をかけるだけで、細かく動きを解説してくれるわけではなかった。技をかけられ、それを反芻することによつて、森は徐々に開祖の柔法により近い技を体得してゆくのである。
さらに、自分がなぜできるのかを、解析した結果、普遍的なコツである「三角技法」にたどり着くのだが、それは、まだ先のことである。
この頃はむしろ、剛法の乱捕に熱中した。
 |
30歳前後の森大範士 |
剛法についても、森は開祖の技に強い印象を受けている。向き合ったときの圧迫感。目の前に拳を寸止めされたときのぞっとするような感覚。「開祖には修羅場をくぐったものにしかない圧倒的な迫力があり、乱捕は怖かった」と森は言う。自分自身、少なからぬ修羅場をくぐっている森の言葉だけに、説得力がある。
総本部の稽古は夜9時に終わる。坂出への最終列車は午後11時発。終電ぎりぎりまで、乱捕の好きな仲間と打ち合った。グロープを着用して、竹の胴をつけ、素面で打ち合う。寸止めではないから、打ち抜く習慣がつく。こうした乱描が少林寺拳法の実戦性を高めていた。そうした練習をしていることに森は誇りを持っていた。
乱捕で、森はどんなに相手が攻めてきても絶対に後ろに下がらないと、若い頃から決めている。下がれば相手は調子づくものだからだ。その場から下がらず、相手の突きがきたら受け崩すと同時に反撃してゆく。小柄な森は大抵の場合、相手よりもリーチが劣るが、相手が打ってきた瞬間に相手の懐に入り、自分の突きが当たる間合をつくるのだ。
相手の猛攻に下がらないのだから、小柄ながら、それだけ身体に力があり、防御技術にも長けていたのだろう。得意なのは下から突き上げるような突きである。相手をインサイドから崩し、インサイドから攻めるのが森のスタイルだ。振り打ちで攻めるようなやり方はしないという。そして、この剛法においても相手の突きを受ける方向を「三角技法」にかなうように行えば、受けられると同時に相手は体勢を崩し、容易に反撃できるのである。
